
映画『Challenged チャレンジド』小栗謙一監督舞台挨拶レポート&インタビュー
2020/09/15
映画『Challenged チャレンジド』の公開記念舞台挨拶が9月13日名古屋・名演小劇場で開催された。
映画『Challenged チャレンジド』は知的障がいのある人々に寄り添ったドキュメンタリー作品を数多く発表している小栗謙一監督の最新作。2012年公開の『幸せの太鼓を響かせて〜INCLUSION〜』で彼らを撮影した後も8年間に渡り監督が成長を見守ってきた長崎の和太鼓演奏集団 瑞宝(ずいほう)太鼓の魂を揺さ振るパフォーマンスや、彼らのグループホームでの生活、世界各地の知的障がい者のいきいきとした生活を捉える。
舞台挨拶前に小栗謙一監督にインタビュー。舞台挨拶の様子とともにお届けする。
舞台挨拶レポート
小栗監督
「今回『Challenged チャレンジド』という映画を作らせていただきましたが、このチャレンジドという言葉をまず説明したいと思います。この言葉は障がいのある方を呼ぶ言葉としてアメリカで生まれ、そして今ではヨーロッパでも使われるようになりました。アメリカでは小学校の教科書にもチャレンジドという言葉が載っていると聞いたことがあります。日本でもチャレンジドという言葉は使われるようになってきていますが、チャレンジドと言ってもそれが障がいのある方のことを言ってるとは思っていただけないことがありますので、まだ普及はしていないのかなと思います。チャレンジドと過去形になっているように感じますが、正しくは‟Be Challenged”。つまり受身形の言葉で始まっています。生まれながらにしてチャレンジすることを与えられた人。そういう意味合いから出ている言葉だという風に思いますが、これは知的障がいだけではなく障がいのある方、全ての方を総じて呼ぶようになっています。私たち生きるものは生まれた時に全員が「これから生きていく間はチャレンジしていくんだよ」と自然界に与えられていると被害者的に考えるのか、それともチャレンジすることを権利として与えてくれていると考えるのか。後者の方で考えてみると非常にポジティブにいろんな夢が広がってくる言葉だなあと。そういう意味ではいい言葉ができたのかなと思いまして、この映画のタイトルとしてつけさせていただきました」

小栗監督
「障がいのある方、特に知的障がいをお持ちの方をテーマとした映画は20年前に『able エイブル』という作品を作った時から始まっています。その時にはアメリカの福祉のあり方を見つめていくために主人公として17歳と19歳の男の子をアメリカに連れて行って、17歳の子はハイスクールに、19歳の子は職業訓練所に毎日通ってもらうことにしたんです。ホストファミリーになってくれたキャサリンとマークという新婚の夫婦がいまして、自分の家に引き取ってくれて3ヶ月家族として過ごしてくれるという約束のもとに生活が始まりました。アメリカの社会がこれだけ懐が広く、大きいんだということを描いた作品でした。そこで障がいのある方への映画は私自身も一区切りつけたというつもりでいましたが、この障がいのある人の社会というのは年々スピードアップしていまして、変化しています。自身の意識も変わっていますし、社会の認識もどんどん変わっています。映画の中にあったように、80年前にはナチスによる殺戮が行われていました。それは障がいのある人を含めて社会で活力として動けない、働けない、力を出せない人は不要という考え方から悲惨なことが起こっていたんです」
小栗監督
「そしてそれはナチスというものが非常に異常だったという風に思いたがる訳ですけども、確かにそうではあってもそれを止めることが出来なかった社会があるわけですね。止められなかっただけではなくて見過ごしてしまう。そして同意した人がどれだけ多かったか。つまりそれでいいんだという社会がおそらく80年前は世界中にあったような気がします。最近専門家会議という言葉がよく使われますが、ナチスの殺戮に至るあの決定というのはまさにその専門家会議によって出されているんですね。医者であったり、精神学者であったり、官僚であったり、弁護士、裁判官、教師であったり、看護士であったり。そういう人たちを専門家とした障がいのある人たちをどうすべきかという会議があって、最終的にはああいう悲惨なことをすることが社会にとってプラスだとヒトラー総統に提案しているわけです。そこにヒトラーはサインしました。ですが、この映画の中でも言っていますが、ヒトラーはサインをしてそれが行われ始めてから8ヶ月後にはストップをかけているんですね。あのヒトラーがです。良くないことだと気がつく。始めたのも彼だし、止めたのも彼なんです。つまりその間は誰も止める人がいなくて、むしろそれに進言した各専門家たちがたくさんいたということなんです。そういう社会があってそしてその後も差別、抑圧、排除された時代が長く続いて、そして今があるんですね」
小栗監督
「瑞宝太鼓の皆さんを見ていただくとお分かりだと思うんですが、想像以上にアーティストとしての力量をお持ちですよね。誰が20年前の彼らにアーティストとしての素養を見ていたでしょうか。おそらく指導している先生達もびっくりしている現象だと思います。それは彼らが努力したことももちろん、周りの人が一生懸命サポートしたことももちろんあります。ですがおそらくもともと彼らにはそういう力があったんですね。しかし彼らはそれを押さえつけられて排除されてきました。「黙ってろ。動くな。何もするな。こっちからしてあげるから」という社会があったんだと思います。それが全部タガが外れて、「いいよ、自分の力でやってごらん」ということを10年20年と続けてきた南高愛隣会というところが彼ら瑞宝太鼓の伸びしろをどんどん成長させてああいうアーティストを作り上げていったという風に思ってください。障がいのある人たちは瑞宝太鼓の皆さんのように同じようなのびしろを持っています。今地球上には2億人知的障がいの人がいると言われています。彼らがやりたいことを伸ばしていく社会があれば、社会全体として地球全体としてどれだけその夢が膨らむでしょうか。そう考えるとインクルージョンの社会というのは非常に大きな地球の財産だと思うんですね。農業生産だって気候変動などで伸びない。資源は掘り尽くしてきている。空気だってだんだん薄くなってきてそして今こういうコロナウイルスというものに悩まされて、どうしたらいいのかと考えているじゃないですか。そういう時こそこのインクルージョンというものが地球を救ってくれるような気がします。この映画にはそういう思いを込めて作っています。ぜひ機会があれば多くの方に観ていただければと思っています」

©2020able映画製作委員会
小栗監督インタビュー
Q.日本だけでなく世界に目を向けて映画を作ろうと思ったきっかけは?
小栗監督
「日本だけで考えているよりはヨーロッパやアメリカという世界の福祉の先進国はどういう動きをしているのかがすごく気になったんです。ただ話の中心は瑞宝太鼓です。瑞宝太鼓がフランスに行くのならそこから広げたら面白いかなと。オムニバスっぽくなっていますが、基本瑞宝太鼓の生き方の派生で観ていくことが出来たかなと思います」
Q.ナレーションは栗原類さんで、とても優しく丁寧な語りでこのドキュメンタリーにぴったりだったと思います。栗原さんにオファーされた理由を教えてください。
小栗監督
「色々な方を考えていたんですが、若い方でいろんな可能性がある方を探して。栗原さんはモデルをやっていらっしゃって今らしい雰囲気で、栗原さんにお願いしたら面白いかなと思ったんです。彼が自身の発達障害をカミングアウトしていることを僕は知らなくて、依頼しようと思った頃にその話を聞いて、栗原さんの著書を読んで色々知った感じです。発達障害があるから彼にお願いしたわけではなく、純粋に雰囲気がいいなと思ってお願いしました。なので僕は彼が英語を話せることも知らなくて。著書を読んだら小さなころはアメリカに住んでいてお父さんがイギリス人だと。なのであの顔立ちなんだと。子どもの頃は英語で育ったのではないかと思い、尋ねたら「僕は英語が第一言語なんです」というので、英語版のナレーションも栗原さんにお願いしています。これはかっこいいんです。英語版は男っぽくて堂々とした感じのナレーションになっています。日本語の方が苦手だと言っていたのでその分、日本語のナレーションは丁寧で誠実な感じなんですね。自分で納得できるまで確認して取り組んでくれました」

小栗謙一監督
Q.瑞宝太鼓さんを監督は長く取材されていてよくご存知だと思います。フランスのナントでの演奏は「ラ・フォル・ジュルネ」も開催されている場所での演奏で本当に素晴らしい演奏でした。カメラを回しながら感じられたことを教えてください。
小栗監督
「彼らは自信満々で堂々として楽しんでいるじゃないですか。ラ・フォル・ジュルネを開催している会場だと聞いて僕も最初驚きました。彼らだからこのぐらいだろうというわけではなくて。そこがやっぱり欧米のすごいところで、彼らを呼ぶのならここでやろうとこの場所を提供してくれますし、瑞宝太鼓のみんながこれに応えてくれるだろうと考えてくださっているわけで。それに向けて彼らは1年半かけて練習していました。そこで演奏できるレベルのものを彼らはきちっと出してくるわけですよね。障害がある人達はまだまだ伸びるよ、可能性を押さえつけていたじゃないかと。絶対に彼らは出来ると信じている国民なんですよね。どうも日本はそうではない。彼らならこれぐらいしか出来ないからこれぐらいでいいかな、これでも贅沢すぎるかなという感覚でイベントを組んでいる国とそうじゃなくてそこで最高のもので立派に勝負してくれと機会と場所を与えてくれる国。もう文化の違いですね。そこは日本は学ばなければいけないところだと思うんです」
Q.一アーティストとして迎えられているのがすごくよくわかります。
小栗監督
「太鼓をフランスに運ぶ飛行機の輸送費だけで1000万円ぐらいかかっていると思いますよ。それも出してくれて呼んでくれるわけです。アーティストとして認めてくれているわけです。障がいのある人に来てもらって太鼓をたたいてもらうのはいいことだというようなお茶を濁すようなイベントではないんです。その幅のくくり方の広さがフランスはすごいなと思います。フランスだけではなく、瑞宝太鼓の皆さんは以前アメリカの桜まつりでも同じことをやっているわけです。ワシントンD.Cのケネディセンターでも演奏しているわけですから」
Q.日本だと支援してあげている感というのがどうしてもあります。
小栗監督
「それはつまらないですよね。その感覚はダメなんです。押さえつけていることと変わらないんですよ」
Q.瑞宝太鼓の方々の中でも引退したり、新しい人が入ったり入れ替えはありますか?
小栗監督
「彼らは20年前にプロになったんですよ。その時からいるのは今1人だけなんです。あとは後から入って来た人。20年前プロになるという時にプロではやれないという人が外れていったり、プロになるなら太鼓ではなく、農業や牛を育てるプロになりたいと選んで行った人もいます。残って太鼓を叩いている人たちが小学校や中学校で演奏をしに行って、それを観た若いタレント志向の強い子が憧れて入ってくるんですね。でもプロの世界は厳しいですからこんなはずじゃなかったと辞めて行く人も多いです。そんな中で今12名在籍しています。彼らはプロの奏者として演奏するだけではなくて昔から南高愛隣会で歴史として受けていた体を動かすリハビリとしての太鼓の演奏のインストラクターもしています」
Q.日本でも瑞宝太鼓の演奏をまた見たいんですが、コロナ禍の状況で瑞宝太鼓の皆さんは今、どのように生活されていますか?
小栗監督
「コロナウイルス感染対策もあって遠征も出来ませんし、長崎の彼らが住んでいる場所の周辺で演奏しているぐらいです。でも学校に行って演奏するわけにも行かないし、養老院などで演奏することもできない。練習をひたすらしているんだと思います。練習の間に時間があるのでその土地でこれからだと稲刈りとかをボランティアで手伝いに行ったりすると思うんですよ。太鼓を叩いているので力はあるので。本当は東京オリンピック・パラリンピックのイベントが色々ありますがその中で演奏するはずだったんですが、それも全部なくなってしまったし、大変ですよね。生活そのものも大変です。彼らは障がい者年金をもらって生活しています。でもその年金だけでは家を借りたり、子どもを育てたり、学校に進学させたりするのは難しいですよね。彼らはプロの太鼓の演奏家としてツアーで回ることで給料として収入を得ています。それをもらっているから生活が成り立っていますが、それがなくなっていますから本当に大変です」
Q.“Challenged”なみなさんを支援している皆さんはもっと社会を良くしたいという思いで活動されているように感じました。長年取材されている監督からはどのように見えていますか。
小栗監督
「インクルージョン(障がいを持った人と健常者を分離するという発想ではなく、障害も一つの個性であると捉え、両者が同じ場所で一緒に過ごすという考え方)という考え方をすると、チャレンジドの人たちがチャレンジするだけでは何も成立していかないですよね。それをサポートしていく人たちも、共生していこうという人たちも一緒になってチャレンジしていくわけですよ。だからチャレンジドの周りの人たちのチャレンジも同時に並行して見えてくるんだと思うんです。撮ろうと思ったのは瑞宝太鼓であり、スウェーデンのチャレンジドの人たちを撮っていくわけですが、当然そこから周りの人たちも別の意味でのチャレンジをし続けているわけです。それがないと共生社会というのは生まれてこないわけですからそういう見え方になるのは当然かなと思います」

©2020able映画製作委員会
Q.今後も監督はチャレンジドな方たちの挑戦を見守っていくような作品を作っていかれますか?
小栗監督
「チャレンジドの人たちを撮り始めてもう20年です。最初『able エイブル』という映画を撮って彼らにはこんなことができるというようなことを1つ見せて、映画を1つ撮り終わった時にこれで終わるかなと思った時期もありましたけど、人間生きていて成長していくわけですから、物事も新しいことがどんどん生まれて価値観も変わっていきますよね。だから撮り続けていかない限り、こういうテーマというのは終わらないと思うんです。僕が生きている間、見続けていく一つのテーマです。『able エイブル』を撮った時に17歳、19歳だった子たちがもうすぐ40歳になるわけです。40歳になったらなったで新しい問題が出てきますよね。40歳、50歳の年齢になると、両親が亡くなったり、兄弟とも疎遠になったり。そうなって一人になったらどうやって社会を生きていくのかという新しい問題が出てきます。それをサポートする社会があるのかとか。瑞宝太鼓もそうですよね。若くて力のあるうちはいいですが、40代にそろそろ入って来る方もいるので今後太鼓が叩けなくなった時に、演奏での収入がなくなってきた時に一律の障がい者年金だけで生活していけるんだろうかというような新たな問題があると思うんですよね。私たちは彼らが声に出しては言えないですからそれを言っていく必要がある。言うにはそれを見ていかないといけないのでずっと見続けていく、それを伝えていくという役割があるんだと思います」
映画『Challenged チャレンジド』https://dsystem.jp/challenged/ は現在名古屋・名演小劇場他で上映中。
おすすめの記事はこれ!
-
 1
1 -
名古屋→東京 福山雅治 1日で駆け抜けた弾丸舞台挨拶でファンに熱い思いを語る!
2024年10月13日、長崎スタジアムシティのこけら落としとしてジャパネットグル ...
-
 2
2 -
映画『安楽死特区』毎熊克哉さん登壇 名古屋大ヒット御礼舞台挨拶レポート
映画『安楽死特区』の大ヒット御礼舞台挨拶が2月8日名古屋ミッドランドスクエアシネ ...
-
 3
3 -
シネマスコーレで上映中。会話劇の魅力。知多良監督初長編作品『ゴールド』
2026年1月26日、名古屋シネマスコーレにて映画『ゴールド』が上映中だ。 映画 ...
-
 4
4 -
『MIRRORLIAR FILMS Season8』公開記念名古屋舞台挨拶レポート
短編映画制作プロジェクト『MIRRORLIAR FILMS Season8』の公 ...
-
 5
5 -
映画『安楽死特区』が問いかけるこれからの日本の「生と死」の境界線―毎熊克哉さん・大西礼芳さん・長尾和宏さんインタビュー
高橋伴明監督が、現役医師である長尾和宏氏によるシミュレーション小説を映画化した『 ...
-
 6
6 -
舞台に命を刻む者の、最期にして最高の輝き(映画『喝采』)
誰もが年を取り衰える。そして昨日まで出来ていたことが急に出来なくなることもある。 ...
-
 7
7 -
義に生きる男たちの姿を見よ(舞台「忠臣蔵」観劇レポート)
名古屋伏見の御園座で堤幸彦監督が演出を手掛ける舞台「忠臣蔵」を観劇した。 舞台の ...
-
 8
8 -
映画『Good Luck』足立紳監督登壇 名古屋シネマスコーレ舞台挨拶レポート
映画『Good Luck』公開記念舞台挨拶が名古屋シネマスコーレで行われ、足立紳 ...
-
 9
9 -
過去と現在を繋ぐ難事件に無敵のバディが挑む!(『映画ラストマン -FIRST LOVE-』)
2023年に「日曜劇場」で放送され、大きな反響を呼んだドラマ「ラストマン-全盲の ...
-
 10
10 -
愛は見える?奇想天外な除霊アクションラブコメディ 映画『見え見え』撮影地愛知で先行公開!
愛知県犬山市で撮影された映画『見え見え』が、12月19日(金)より愛知ミッドラン ...
-
 11
11 -
ANIAFF 開幕!第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル オープニングセレモニーレポート
2025年12月12日(金)、「第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメー ...
-
 12
12 -
SF映画の脚本 キャスティング 世界観を彩る特殊効果の秘密 『ブラックホールに願いを!』渡邉聡監督 × 『センターライン』『INTER::FACE 知能機械犯罪公訴部』下向拓生監督 スペシャル座談会(後編)
『ブラックホールに願いを!』公開を記念し、渡邉聡監督と脚本協力を務めた下向拓生監 ...
-
 13
13 -
SF映画の脚本 キャスティング 世界観を彩る特殊効果の秘密 『ブラックホールに願いを!』渡邉聡監督 × 『センターライン』『INTER::FACE 知能機械犯罪公訴部』下向拓生監督 スペシャル座談会(前編)
第一線の特撮現場で活躍している若手スタッフが集結! 新進気鋭の映像制作者集団「S ...
-
 14
14 -
映画『Good Luck』は「ととのう系」!? 自然とサウナと旅先の出会い(『Good Luck』足立紳監督、足立晃子プロデューサーインタビュー)
2025年12月13日からシアター・イメージフォーラム、12月27日から名古屋シ ...
-
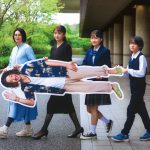 15
15 -
兄のことをひたすら考える終いの4日間(映画『兄を持ち運べるサイズに』)
『湯を沸かすほどの熱い愛』や『浅田家!』で数多くの映画賞を席捲し、一貫して家族の ...
-
 16
16 -
映画『Good Luck』先行上映記念 足立紳監督&足立晃子プロデューサー 舞台挨拶レポート
11月24日「NAGOYA CINEMA Week 2025」の一環として、足立 ...
-
 17
17 -
本物の武道空手アクションがここに!映画『TRAVERSE2 -Next Level-』豊橋で先行公開、完成披露試写会 開催!
武道空手アクション映画の金字塔となる二部作の完結編、映画『TRAVERSE2 - ...
-
 18
18 -
極寒の会津ロケからベルリン映画祭出品へ! 魂の舞と幽玄の世界が描き出す人間の複雑な心境(映画『BONJI INFINITY』初号試写会 舞台挨拶レポート )
2025年11月3日、映画『BONJI INFINITY(ボンジ インフィニティ ...
-
 19
19 -
日本初ARRIが機材提供。美しきふるさとの映像と音に触れ、自身を回顧する(映画『郷』小川夏果プロデューサーインタビュー)
数々の国際映画祭で評価を重ねてきた鹿児島出身の新進気鋭の伊地知拓郎監督が、構想か ...
-
 20
20 -
映画『佐藤さんと佐藤さん』名古屋先行上映会舞台挨拶レポート。岸井ゆきのさん、宮沢氷魚さん、天野千尋監督登壇
映画『ミセス・ノイジィ』の天野千尋監督の最新作は夫婦の変化する15年間を描く、オ ...
-
 21
21 -
運命さえも覆せ!魂が震える慟哭のヒューマン・ミステリー(映画『盤上の向日葵』)
『孤狼の血』などで知られる人気作家・柚月裕子の小説『盤上の向日葵』が映画化。坂口 ...
-
 22
22 -
本から始まるストーリーは無限大に広がる(映画『本を綴る』篠原哲雄監督×千勝一凜プロデューサー インタビュー&舞台挨拶レポート)
映画『本を綴る』が10月25日から名古屋シネマスコーレで公開されている。 映画『 ...
-
 23
23 -
いつでも直球勝負。『おいしい給食』はエンターテイメント!(映画『おいしい給食 炎の修学旅行』市原隼人さん、綾部真弥監督インタビュー)
ドラマ3シーズン、映画3作品と続く人気シリーズ『おいしい給食』の続編が映画で10 ...
-
 24
24 -
もう一人の天才・葛飾応為が北斎と共に生きた人生(映画『おーい、応為』)
世界的な浮世絵師・葛飾北斎と生涯を共にし、右腕として活躍したもう一人の天才絵師が ...
-
 25
25 -
黄金の輝きは、ここから始まる─冴島大河、若き日の物語(映画 劇場版『牙狼<GARO> TAIGA』)
10月17日(金)より新宿バルト9他で全国公開される劇場版『牙狼<GARO> T ...
-
 26
26 -
「空っぽ」から始まる希望の物語-映画『アフター・ザ・クエイク』井上剛監督インタビュー
村上春樹の傑作短編連作「神の子どもたちはみな踊る」を原作に、新たな解釈とオリジナ ...
-
 27
27 -
名古屋発、世界を侵食する「新世代Jホラー」 いよいよ地元で公開 — 映画『NEW RELIGION』KEISHI KONDO監督、瀬戸かほさんインタビュー
KEISHI KONDO監督の長編デビュー作にして、世界中の映画祭を席巻した話題 ...
-
 28
28 -
明日はもしかしたら自分かも?無実の罪で追われることになったら(映画『俺ではない炎上』)
SNSの匿名性と情報拡散の恐ろしさをテーマにしたノンストップ炎上エンターテイメン ...
-
 29
29 -
映画『風のマジム』名古屋ミッドランドスクエアシネマ舞台挨拶レポート
映画『風のマジム』公開記念舞台挨拶が9月14日(日)名古屋ミッドランドスクエアシ ...
-
 30
30 -
あなたはこの世界観をどう受け止める?新時代のJホラー『NEW RELIGION』ミッドランドスクエアシネマで公開決定!
世界20以上の国際映画祭に招待され、注目されている映画監督Keishi Kond ...
-
 31
31 -
『ぼくが生きてる、ふたつの世界』の呉美保監督が黄金タッグで描く今の子どもたち(映画『ふつうの子ども』)
昨年『ぼくが生きてる、ふたつの世界』が国内外の映画祭で評価された呉美保監督の新作 ...
-
 32
32 -
映画『僕の中に咲く花火』清水友翔監督、安部伊織さん、葵うたのさんインタビュー
Japan Film Festival Los Angeles2022にて20歳 ...
-
 33
33 -
映画『僕の中に咲く花火』岐阜CINEX 舞台挨拶レポート
映画『僕の中に咲く花火』の公開記念舞台挨拶が8月23日岐阜市柳ケ瀬の映画館CIN ...
-
 34
34 -
23歳の清水友翔監督の故郷で撮影したひと夏の静かに激しい青春物語(映画『僕の中に咲く花火』)
20歳で脚本・監督した映画『The Soloist』がロサンゼルスのJapan ...
-
 35
35 -
岐阜出身髙橋監督の作品をシアターカフェで一挙上映!「髙橋栄一ノ世界 in シアターカフェ」開催
長編映画『ホゾを咬む』において自身の独自の視点で「愛すること」を描いた岐阜県出身 ...
-
 36
36 -
観てくれたっていいじゃない! 第12回MKE映画祭レポート
第12回MKE映画祭が6月28日岐阜県図書館多目的ホールで開催された。 今回は1 ...
