
EntaMirage! Entertainment Movie
誰もが主役。名もなきエキストラとしての人生とは 監督集団「5月」(関友太郎監督、平瀬謙太朗監督、佐藤雅彦監督)インタビュー(映画『宮松と山下』)
2022/11/10
東京藝術大学大学院映像研究科佐藤雅彦研究室を母体とした監督集団「5月」から生まれた初の長編映画『宮松と山下』。
エキストラとして名もなき人を来る日も来る日も、時には1日に何回も殺されながら演じている記憶喪失の男・宮松。彼はロープウェーの職員として働きながら、名もなき人を演じることに落ち着きを感じていた。そんな宮松のもとに彼の過去を知る人物が訪ねてくる。宮松はどうやら昔はタクシードライバーとして働いていたらしい。彼は妹夫婦と一緒に暮らすことになるが…。
エキストラという主役ではない人物を主役に据え、観客に多様な驚きを提供してくれるこの作品。香川照之が複雑な役どころを見事に演じ分ける。
3人で映画を作るとはどういうものなのか、どのように映画を作っていったのか。監督集団「5月」の3人(関友太郎監督、平瀬謙太朗監督、佐藤雅彦監督)に伺った。
Q.作品を3人の監督で作るということが興味深いです。3人で話を作っていくための合意形成、「決めていく」というのは実際、具体的にどうやっていかれたのでしょうか
平瀬監督
「もう10年以上も3人で活動しているので、かなりの時間を一緒に過ごしてきました。4、5時間の打ち合わせを毎週欠かさず続けてきたので、もう何千時間も映画について話し合ってきたことになります。言葉にしなくても、お互いが何を考えているかも分かりますし、それぞれの意思が統合されて ”3人でひとり” という独特の感覚になってきているので、合意形成はあまり難しくありません。例えば、新しいアイデアを思いついた時も、あまり一人で考えすぎないで、すぐに他の2人にも共有して3人で検討します。すると、3人の統合された感覚が、そのアイデアの価値をすぐに見抜いてくれます。何か難しい合意形成のプロセスがあるわけではなくて、感覚的にピンとくるんですね。面白いのはアイデアがダメな時で、2人に共有して3人のものになった瞬間、自分でも「これは違うな」と客観的に分かるので非常に不思議です」
Q.エキストラは主役ではないですよね。そのエキストラをやる人というのを主役にしようと思ったきっかけ、面白いなと思って制作を進めていった流れを教えていただきたいと思います
佐藤監督
「これは関から出たアイディアなんです。関は、東京藝術大学の大学院を卒業した後、NHK に入ったんですね。ドラマ部門に配属されて。その先の話は、では本人から」
関監督
「ドラマ部で最初の現場に入ったのが、京都の松竹撮影所だったんですが、時代劇もドラマも初めての現場で。最初だったので担当したのがエキストラ担当だったんです。何日間もエキストラの皆さんを見ていると、午前中に町人役だったのに、途中で衣装替えが入って午後からは侍としてバスに乗って出て行ったりとか、1日の中でいろんな人間をやっていたりするのはそれだけで面白いなと思いました。それと、侍たちの斬り合いのシーンで、侍が大勢いるように見せないといけないので、1人が1回斬られて倒れても、もう1度立ち上がって今度は別の侍として斬り合いに加わり、そしてまた誰かに斬られる、という撮影をしていました。そのエキストラとしての振る舞いだけを切り取って見ると、すごく変わったことをやっていて、面白いなと思いました。それが最初でした。また、もしそれを映画にする場合は、例えばエキストラとしていろんな役柄を演じている部分と、彼の地の生活の部分を全く同じトーンで並列につなげていったら面白い映画体験になるんじゃないかなというのがあったんです」

Q.時代劇のシーンがエキストラの部分でも多かったのは松竹撮影所での経験からなんですか
関監督
「そうですね、やっぱり時代劇って絵が面白いというのはありますね。侍の格好のまま中華料理屋にラーメンを食べに行くシーンもあったと思うんですが、あれは実際自分が見てびっくりしたからなんです。昼休憩になるとみんながぞろぞろと役衣装のまま撮影所から出て行って。撮影所のすぐ近くに中華料理屋があるんですけど、武士とか江戸の町人たちが衣装の中から自分の財布を取り出してお金を払っているのを見て「なんだこの光景は!」と。あとやっぱり、いろんな役を見せるのであれば、その落差やギャップがあったほうが面白いと思うんです。そこで、一番落差が大きくできるのは時代劇のはずだと。現代の中だけで役が変わっていくよりも、時代が違うというのは大きいかなと思って。それで時代劇のシーンが多めになっているような気がします。
Q.キャスティングで香川さんの名前が挙がった経緯を教えてください
平瀬監督
「実はこの企画については、アイデアがが出てから長らくペンディング状態といいますか5、6年踏み出せずにいました。その理由がキャスティングです。主人公の宮松という人物は、映画にとっては物語を引っ張っていく強い存在感が必要な反面、劇中ではエキストラという役どころで、背景に潜むような存在感の無さも必要です。この矛盾する二面性を誰なら成立させる事ができるのか、ずっと答えが出ませんでした。でも、ある時、香川さんの名前が出て。その瞬間、3人とも香川さんなら宮松になれることがパっと分かって。それでこの企画がやっと立ち上がりました。逆に言うと、香川さんに断られたらこの企画はやらなかったと思います。誰か代えのきくキャスティングではなく、香川さんしかありえませんでした」
Q.オファーした時の香川さんの反応は?
関監督
「衣装合わせの時に脚本が面白かったと言っていただいて。我々が説明する前から、脚本を深く読み込んでいただき、実際にどうやって宮松を演じていくか、既にいくつものイメージが出来上がっているようでした」
Q.香川さんと言えば最近はドラマでも大きな動きというかちょっと強烈な芝居を要求されるオファーが続いていたのかなと思うんですね。ご本人の中でもすごく面白いなと脚本を読んで思われたのかもしれませんね
佐藤監督
「私が特になのかもしれないですけど、テレビを全く見ないので、半沢直樹というドラマを観ていないので大げさな演技は知らないんですね。私の中では、香川さんといえば映画『ゆれる』なんです。あの演技がすごく印象的で驚きでもあったので、この宮松ができる人は誰かなと思ったときに、香川さんがすごくいいなと。あまり民放ドラマの影響を私が受けていなかったのが、幸いしたのかもしれないです」

Q.現場で香川さんと話して作っていった部分もありますか
佐藤監督
「香川さんは現場に入る前にずいぶん台本を読み込んでくれてたんです。香川さんだけじゃなくて中越さんもそうですけど、この映画の中の、宮松像とはどういうものか、山下像とはどういうものと自分なりに考えてくれて、それで現場に入ってくださったんです。ただやっぱり暗中模索のところも香川さんにはあって。例えばロープウェーから降りて、階段を降りるときに宮松ならどうやって降りるのかなと、トントントンと降りて、やっぱり違うよね、宮松はもうちょっとなんかしょんぼり降りるよねと。ちょこちょこ歩いてトン、ちょこちょこ歩いてトンと降りる。あ、これだねとみんなで確認するとか。悩んでいたことを現場で我々にプレゼンテーションしたんです。それと香川さんは我々に「この現場には映画がある」と言ったんです。どういうことですかと聞いたら、例えば民放のドラマはこれを撮ったら次、撮ったら次とパンパン撮影が進んでいくんですよ。時間的そして経済的効率というのはあるかもしれませんけど。ここにはみんなでこの主人公はどういう気持ちで、どんな表情をするのかを悩む時間があると。それを香川さん流に言ったのが「この現場には映画がある」だったようで。その言葉を言われて嬉しかったですね」
Q.香川さん以外のキャスティングも魅力的です。どんな風に決まっていったのでしょうか
平瀬監督
「一番すぐに決まったのは尾美としのりさんです。尾美さん演じる谷の第一声は「山下だよな」ですが、それを言うのは誰がいいだろう、と議論して尾美さんの名前はすぐに上がりました。このように、私たちはいつも、その人物の代表的なセリフを例にして考えていきます。例えば、健一郎だったら「お兄さんといえば日本酒だったじゃないですか」を言えるのは誰か。たくさん悩んで、津田寛治さんのお名前が出た時に、みんながそれだ!と」
佐藤監督
「別の観点からちょっと補足すると、我々は海外の国際映画祭でも上映したいと考えていたので、認知的な“人種効果”を考慮しています。例えば我々がメキシコの映画を観たとすると始めの頃は、メキシコ人の主役とメキシコ人の脇役の区別がなかなかつかないですよね。同じように、ヨーロッパの人にとって人種として遠い日本人の区別をするのは難しいんですよ。それで香川さんの髪の色と異なる白髪の人ではっきり区別ができる人、演技的にもすごくいい人、しかも人柄が根っからいい、そんな条件から、僕は尾美さんが出たんですよね。そういうところも加味してサブキャストを決めました」
Q.野波麻帆さんや大鶴義丹さんはどういう観点からキャスティングされたんでしょうか
佐藤監督
「野波さんは、以前から私が個人的に好きで。派手な感じで性格が良くて屈託のない。なんかそういう人がそこにいて欲しかったのでお願いしました。大鶴義丹さんも結構僕は昔から注目していて、2枚目の俳優としているんだけど、何か奥底にいろんなものが入っているというところで大鶴さんがピンと浮かんだんですね」
Q.中越典子さんはちょっとイメージとは違う気もします
平瀬監督
「中越さんの世の中でのイメージってもっと元気で、パッと明るくて、みんな楽しくいこう!みたいな。でも今回はあえてそうじゃない役柄でお願いしました」
佐藤監督
「明るくて元気な中越さんも新しい中越さん像を作るということに、すごく興味がおありだったんです」
関監督
「中越さんが演じる藍は一見、周りには明るく振る舞うんだけど、どことなく影が漂っているキャラクターでもあります。その影の部分をどうやって表現するかという話で中越さんの方から提案があって、例えば目のクマとかは普段メイクで消しているそうなんですが、あえてクマを残した状態でのメイクにしてみたい、という話をいただいたんです。そういった提案はとても嬉しかったですし、実際にそのアイデアを取り入れて、撮影に入りました」
佐藤監督
「中越さんも初日あたりは一番悩んでいて、「これでいいのかしら?」と言っていたんですが、2日目にはすっかり掴んでいて、香川さんも「中越さん、変わった」って僕達に言っていました。きれいになったし、内容的にも変わったと。もう演技が入っちゃったんです。それはすごく良かったです」
Q.今回が初めての長編映画ですが、苦労したところを教えて下さい
佐藤監督
「編集ですね。この映画はいわゆる地か、劇かわからないというのを並べる手法で、鑑賞者に新しい映像体験をさせるわけですね。自分が信じていた世界が実は劇だったという、それをどういう風に編集したら一番効果的に出るのかというので、ものすごくバージョンを作りました。そこはすごい苦労しましたね」
関監督
「僕らの作品は現場では完結しなくて。現場で感じたことももちろんの事なんですが、現場でどんなに良いテイクが撮れたとしてもそこで完全に安心することはできないんです。それは、この映画の映像手法が成立するかどうかは、どうしても編集の段階になってみないと探れない部分があるからです。現場でいろんなパターンを撮るというのは撮影スタッフにストレスを与えてしまうこともありますし、色々と辛い思いをすることもあります。けれど、この作品の肝である映像手法の良し悪しを最終的に決定できるのは、撮影現場ではなくて編集の場です。だからこそちょっと違うテイクを撮ってみようとか、すごい表情が撮れたんだけど別パターンも、など、そういう試行錯誤は、時間が許す限りというか、時には予定時間を越えてまで粘っていたような気がします」

Q.何年も仲良く3人でずっとやってこられたわけなんですが、東京藝術大学の大学院の映像研究科が原点ですね。東京藝術大学大学院映像研究科とはどんなところですか
佐藤監督
「東京藝大には昔から美術学部と音楽学部があるのはご存知だと思います。それは明治時代に設置されました。ところが現在世界で生まれている表現のかなりの部分は動画なんですよね。それで、やっぱり映像を研究する場所、教育する場所が必要だということで、映像研究科構想が1990年代にできてその後2006年に今のメディア映像専攻が出来、私はそこの教員でした。佐藤研究室では、週に1回研究会が開かれ、そこでみんなの考えているテーマとか、制作の進捗状況あるいは試作を発表するという時間を共にする2年間があるんですね。彼らは研究室の5期生だったんですけれども、非常に優秀な年代で、個人制作の出来もすごく良かったので、普通藝大ではみんなでプロジェクトをやるというのはなかなかないんですが、この人たちとだったらできるなと思って短編映画を作るプロジェクト・c-projectを立ち上げました。そこでアイディアを出していくんです。最初に私もアイディアをいっぱい出し、みんなもいっぱい出すんですが、みんな、なかなか、うんと言わないんです。でもあるアイディアが出た時に全員が「それです!」となったんですね。それはすごく面白いんです。インタビューの最初に合意形成という話がありましたが、合意形成自体はなかなかに手間取ってすごく大変な手順なんです。ですが、この人たちとだったら一瞬でできるとその時、私は感じました。みんなも多分そう思ったんだと思います。一瞬なんです。いい時はいいって皆が言うんですよ。これでいけると私は思いましたね。合意形成について我々はそれをクリアしていて、いいと思うことが一致するんですよ。そこに全然ストレスもエネルギーもなくて、そこが我々が監督集団「5月」として成立しているすごく大きなことだなと思いました。先ほど仲良しとおっしゃられましたけど、それはちょっと違いますね(笑)同士に近い感じです」
Q.合意形成が出来たチームで作る良さとはどんなところですか
関監督
「やっぱり意見を当てられる環境があるというのは制作する上でとても助かります。言ってみた瞬間に自分でもわかるんですよ。今自分が言ったことは面白くなかったなと。頭の中で考えているときはこれいいアイディアなんじゃないかとか思っていたのに、口にした瞬間に大したことないな、これじゃあ全然進まないなというのが自分でもわかる。もちろん、その逆もあります。話してみた途端、「これは面白くなるかも」とにわかに手応えをつかんだり。不思議なことに、この2人にアイデアを当てた途端に良し悪しがわかるんです。だから、良い悪いの判断が一度、3人の監督の中で出来ているわけです。もしこれが1人だったら、初めて口に出すのが大勢のスタッフの前ということになるので、言い出した後で「これ違うかもしれない」と思っても遅いわけで、監督というチームの中で話し合った上で「これをやったら面白いんじゃないか」とかを決めていける。そういう部分が複数監督でやっている強みですね。」
平瀬監督
「仲はすごくいいですけど、じゃあ休日に遊びに行ったり、飲みに行くかというとそれは全くなくて(笑)私たちの関係は、お互いがお互いを見ているのではなくて、3人があるひとつの理想を見ていて、そこに一緒に進んでいく仲間という感覚です。そういうチームの在り方というのは、やはり研究室時代に作られた気がします。研究室がそのまま社会に出て活動しているような。他のプロジェクトでもチームでものを作ることはよくありますが、それとは全然違って、3人だからこそ独特の連帯感があるような気がします」

左から関友太郎監督、平瀬謙太朗監督、佐藤雅彦監督
見える風景が同じ。これは何よりも心強い。同じ目標に向けて進んでいく同士。監督集団「5月」が議論しながら作り上げた『宮松と山下』。どこまでが劇でどこまでが地なのか。その境界線が限りなく曖昧なのがこの作品の面白さだ。2回目を観たいなあと今すごく思っている。エキストラ経験がある身としては懐かしい自分の記憶とも重なった。
映画『宮松と山下』
https://bitters.co.jp/miyamatsu_yamashita/
11/18(金)新宿武蔵野館、渋谷シネクイント、シネスイッチ銀座ほか全国ロードショー。東海3県では愛知 伏見ミリオン座、MOVIX三好、ミッドランドスクエア名古屋空港、大垣コロナシネマワールドで11/18(金)より、三重 伊勢進富座でも公開予定。
取材者
ライター:涼夏
普段は名古屋、岐阜で司会、映画の取材をメインに活動中。たまに役者、朗読も。
おすすめの記事はこれ!
-
 1
1 -
愛は見える?奇想天外な除霊アクションラブコメディ 映画『見え見え』撮影地愛知で先行公開!
愛知県犬山市で撮影された映画『見え見え』が、12月19日(金)より愛知ミッドラン ...
-
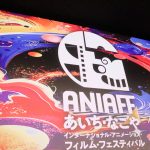 2
2 -
ANIAFF 開幕!第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル オープニングセレモニーレポート
2025年12月12日(金)、「第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメー ...
-
 3
3 -
SF映画の脚本 キャスティング 世界観を彩る特殊効果の秘密 『ブラックホールに願いを!』渡邉聡監督 × 『センターライン』『INTER::FACE 知能機械犯罪公訴部』下向拓生監督 スペシャル座談会(後編)
『ブラックホールに願いを!』公開を記念し、渡邉聡監督と脚本協力を務めた下向拓生監 ...
-
 4
4 -
SF映画の脚本 キャスティング 世界観を彩る特殊効果の秘密 『ブラックホールに願いを!』渡邉聡監督 × 『センターライン』『INTER::FACE 知能機械犯罪公訴部』下向拓生監督 スペシャル座談会(前編)
第一線の特撮現場で活躍している若手スタッフが集結! 新進気鋭の映像制作者集団「S ...
-
 5
5 -
映画『Good Luck』は「ととのう系」!? 自然とサウナと旅先の出会い(『Good Luck』足立紳監督、足立晃子プロデューサーインタビュー)
2025年12月13日からシアター・イメージフォーラム、12月27日から名古屋シ ...
-
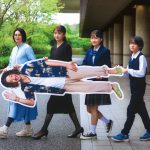 6
6 -
兄のことをひたすら考える終いの4日間(映画『兄を持ち運べるサイズに』)
『湯を沸かすほどの熱い愛』や『浅田家!』で数多くの映画賞を席捲し、一貫して家族の ...
-
 7
7 -
映画『Good Luck』先行上映記念 足立紳監督&足立晃子プロデューサー 舞台挨拶レポート
11月24日「NAGOYA CINEMA Week 2025」の一環として、足立 ...
-
 8
8 -
本物の武道空手アクションがここに!映画『TRAVERSE2 -Next Level-』豊橋で先行公開、完成披露試写会 開催!
武道空手アクション映画の金字塔となる二部作の完結編、映画『TRAVERSE2 - ...
-
 9
9 -
極寒の会津ロケからベルリン映画祭出品へ! 魂の舞と幽玄の世界が描き出す人間の複雑な心境(映画『BONJI INFINITY』初号試写会 舞台挨拶レポート )
2025年11月3日、映画『BONJI INFINITY(ボンジ インフィニティ ...
-
 10
10 -
日本初ARRIが機材提供。美しきふるさとの映像と音に触れ、自身を回顧する(映画『郷』小川夏果プロデューサーインタビュー)
数々の国際映画祭で評価を重ねてきた鹿児島出身の新進気鋭の伊地知拓郎監督が、構想か ...
-
 11
11 -
映画『佐藤さんと佐藤さん』名古屋先行上映会舞台挨拶レポート。岸井ゆきのさん、宮沢氷魚さん、天野千尋監督登壇
映画『ミセス・ノイジィ』の天野千尋監督の最新作は夫婦の変化する15年間を描く、オ ...
-
 12
12 -
運命さえも覆せ!魂が震える慟哭のヒューマン・ミステリー(映画『盤上の向日葵』)
『孤狼の血』などで知られる人気作家・柚月裕子の小説『盤上の向日葵』が映画化。坂口 ...
-
 13
13 -
本から始まるストーリーは無限大に広がる(映画『本を綴る』篠原哲雄監督×千勝一凜プロデューサー インタビュー&舞台挨拶レポート)
映画『本を綴る』が10月25日から名古屋シネマスコーレで公開されている。 映画『 ...
-
 14
14 -
いつでも直球勝負。『おいしい給食』はエンターテイメント!(映画『おいしい給食 炎の修学旅行』市原隼人さん、綾部真弥監督インタビュー)
ドラマ3シーズン、映画3作品と続く人気シリーズ『おいしい給食』の続編が映画で10 ...
-
 15
15 -
もう一人の天才・葛飾応為が北斎と共に生きた人生(映画『おーい、応為』)
世界的な浮世絵師・葛飾北斎と生涯を共にし、右腕として活躍したもう一人の天才絵師が ...
-
 16
16 -
黄金の輝きは、ここから始まる─冴島大河、若き日の物語(映画 劇場版『牙狼<GARO> TAIGA』)
10月17日(金)より新宿バルト9他で全国公開される劇場版『牙狼<GARO> T ...
-
 17
17 -
「空っぽ」から始まる希望の物語-映画『アフター・ザ・クエイク』井上剛監督インタビュー
村上春樹の傑作短編連作「神の子どもたちはみな踊る」を原作に、新たな解釈とオリジナ ...
-
 18
18 -
名古屋発、世界を侵食する「新世代Jホラー」 いよいよ地元で公開 — 映画『NEW RELIGION』KEISHI KONDO監督、瀬戸かほさんインタビュー
KEISHI KONDO監督の長編デビュー作にして、世界中の映画祭を席巻した話題 ...
-
 19
19 -
明日はもしかしたら自分かも?無実の罪で追われることになったら(映画『俺ではない炎上』)
SNSの匿名性と情報拡散の恐ろしさをテーマにしたノンストップ炎上エンターテイメン ...
-
 20
20 -
映画『風のマジム』名古屋ミッドランドスクエアシネマ舞台挨拶レポート
映画『風のマジム』公開記念舞台挨拶が9月14日(日)名古屋ミッドランドスクエアシ ...
-
 21
21 -
あなたはこの世界観をどう受け止める?新時代のJホラー『NEW RELIGION』ミッドランドスクエアシネマで公開決定!
世界20以上の国際映画祭に招待され、注目されている映画監督Keishi Kond ...
-
 22
22 -
『ぼくが生きてる、ふたつの世界』の呉美保監督が黄金タッグで描く今の子どもたち(映画『ふつうの子ども』)
昨年『ぼくが生きてる、ふたつの世界』が国内外の映画祭で評価された呉美保監督の新作 ...
-
 23
23 -
映画『僕の中に咲く花火』清水友翔監督、安部伊織さん、葵うたのさんインタビュー
Japan Film Festival Los Angeles2022にて20歳 ...
-
 24
24 -
映画『僕の中に咲く花火』岐阜CINEX 舞台挨拶レポート
映画『僕の中に咲く花火』の公開記念舞台挨拶が8月23日岐阜市柳ケ瀬の映画館CIN ...
-
 25
25 -
23歳の清水友翔監督の故郷で撮影したひと夏の静かに激しい青春物語(映画『僕の中に咲く花火』)
20歳で脚本・監督した映画『The Soloist』がロサンゼルスのJapan ...
-
 26
26 -
岐阜出身髙橋監督の作品をシアターカフェで一挙上映!「髙橋栄一ノ世界 in シアターカフェ」開催
長編映画『ホゾを咬む』において自身の独自の視点で「愛すること」を描いた岐阜県出身 ...
-
 27
27 -
観てくれたっていいじゃない! 第12回MKE映画祭レポート
第12回MKE映画祭が6月28日岐阜県図書館多目的ホールで開催された。 今回は1 ...
